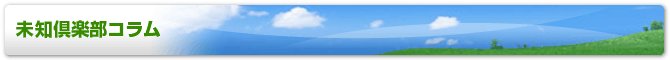美味しいとは
2006年12月11日
先週、愛媛県の道の駅瀬戸農業公園の成本様のところにお邪魔しました。
成本様は頻繁に駅長コラムへご投稿頂いており、その中で地域での懸命なお取り組み姿勢と本質を突いた問題点をご披露くださっています。私が常々感謝と尊敬の念を抱いている方の一人です。
お伺いした際、成本様行きつけのレストラン‘まりーな亭’で食事をご一緒させていただきました。‘まりーな亭’はホームページ上でも紹介してくださっています。
http://www.michi-club.jp/detail/station.php?stationid=000083
この食事会には、田村菓子舗三代目の田村さん、そして‘まりーな亭’の宇都宮オーナーシェフも加わってくださり、さながらタウンミーティングようなの雰囲気の中、延々4時間に亘り色々な話をしました。
話が地域産品や郷土料理に及んだとき、成本様より‘地域では自分達が作った料理、米、野菜、果物は皆この世で一番美味しいと胸を張っているが、果たしてそれだけで良いのか’というご意見が挙がりました。大変興味深いご指摘でした。
この点について成本様と議論を深めることとなりました。その時の話を踏まえ、本日のコラムでは‘美味しさ’について述べたいと思います。
私は全国津々浦々飛び回っております。各地で出会う地域の料理は何れも珍しく、そしてありがたく、そして美味しいと思っています。しかし、一方でその美味しさとは何なのか、実は私はずっと考えてきました。
料理を表現する言葉には、甘い、塩辛い、しょっぱい、苦い、酸っぱいなどがあります。それらの言葉を超えたところに‘美味しい‘という言葉が共通して 君臨してしまうと、全ての料理は「美味しい」か「美味しくない」かに集約されてしまいます。とりわけ我々日本人は基本的には同じような食文化を原点に持っていますのでそれ以外の表現を上手に生み出して来なかったのではないか、と感じてしまうのです。
たとえばアラブ料理です。羊料理には独特の臭みがあり、現地の人たちの味覚はその臭みそのものを愛好するのですが、大抵の日本人にとってはその独特の匂いは親しみのないものです。日本人がアラブの羊料理の美味しさを堪能するためには時間と経験が必要です。
また、かのフランス料理にしても、鳩だとかジビエだとか腎臓とかが出てくるとやはり独特の臭みと苦味があり、これも本当に味わうには経験を要します。
このような異文化の食については、単に‘美味しい’と表現しても、‘でもこれは主観でしょう’と容易に異論が出てくる可能性があります。また一方で、その美味しさを堪能できないことは食文化の違いに過ぎません。従って、食文化の相異を尊重する立場からは、‘美味しい’とは別の表現を使うことが望ましいのです。
しかるに日本料理。日本人であれば殆どの料理が許容範囲内にあります。たとえば「いしり」と呼ばれる能登半島の魚醤などは一見すると強烈な発酵臭を持ってはいますが、地元の料理人の手に掛かれば間違いなく美味しいです。
また、お米はどうでしょうか。色々な地域でその地の地域米を食べる機会があります。どの米も美味しいです。酒にしても地域の人が自信を持って紹介する地酒は外れはありません。果物もしかりです。
しかしそうすると地元の食品や料理は全て美味しいということになってしまい、差別化は難しくなります。
さて、再びフランスの話。フランスと言ったらワイン文化の中心です。生産量であればお隣のイタリアの方が多いですし、歴史でいえば中近東やギリシャの方がよっぽど古いかもしれません。しかし、ワインといったらフランスが一番です。それに異論を呈する人はワインを知らない人だと烙印されてしまうほど、フランスワインは絶対的な力を持っています。
何故か? それは生産量でもなく歴史の古さでもありません。
美味しさというものを学問的に追求しそして評定基準をしっかり作った初めての国がフランスだからです。もっともそれ以前にも、ブルゴーニュのシャンベルタンをナポレオンがこよなく愛し戦場にも必ず持参したとか、駐仏大使だったトーマスジェファーソン第三代米大統領が離任の際にグラーブのオーブリオンを大量に酒樽でアメリカへ持ち帰ったとか、そんな逸話がフランスワインの権威や伝説を生み出した、ということも事実です。
しかし、この世にフランスワインが君臨しているのは、19世紀半ばのパリ万博に備えて、ボルドーにおける格付け作業を地元のワイン取引業者卸組合が行ったからです。彼らはその作業をするに当たり、味、色、香りにおいて厳格な基準を設けました。単なる美味しいという主観的な基準を初めて排除したとも言えます。そうしなければボルドーは、伝統ある産地であるブルゴーニュに勝ち目がなかったからです。
その後は フランス国家を挙げて、全土のワイン及び生産地を対象に、品種、 成分、地質、土壌、 気候、湿度、温度、日照時間、醸造方法等を調査し独自の品質管理制度(AOC)を確立しました。 このような地道な学究と品質維持向上の努力とが相俟って、フランスはワイン王国となることが出来たのです。技術と資本だけでなく言語力、文化力の違いが現在の地位を築いたとも言えます。
ところで、日本ではいまだに‘このワインは美味しい’という表現を平気で使う人がいますが、フランスでは美味しいとは言いません。‘美味しい’に当たる単語である‘Bon’という表現は、テースティングの時にのみ使われ、ソムリエから提案されたボトルをこのまま頂きますよ、という意味合いの言い回しになります。否定形の‘Pas Bon’も味の良し悪しではなく、酸化が進み過ぎているので受け取れない、そんな意味に当たります。
もっともワインの大家なら、保存状態まで分かった上で厳しく‘Non’ということもあるでしょうが。
それでは、日本の料理と素材に話を戻しましょう。地域の人が一生懸命お作りになったものには、基本的に味や品質の面で間違いはありません。しかし、生産や調理の方法において、たとえば、成分、糖度、気候、気温、土壌、農薬散布や施肥の方法、技術、手入れ、伝統、等々、それぞれについて異なるにも関わらず、その帰結とする表現が全て‘美味しい’ということに行き着くのであれば、それはいつになっても本質的な差別化はできないということとなります。
もともと有名な地域は断然有利ですが、そうでない他の地域の場合は、相当な努力をしても‘美味しい’の一言で片付けられてしまい、なかなか浮かばれないということになります。
ここで‘浮かばれる’‘浮かばれない’と言ったのは、マーケットで高く売れるか安値で引き取られるかと言うこととも同義で、地域にとっては死活問題です。それでも現実には、国産米でも品種や産地によって数倍の価格の差がついています。本当にそれほど価値に差があるかどうか、私の舌では判別できません。同じ海域で獲れる魚介類も、水揚げ地が違うだけで異なった価格が付くという話をよく聞きます。
そうした現象を‘ブランド力の違い’と言って納得する人が多いですが、私は常々、本来のブランドとは単なる雰囲気だけでなく、その前提としての科学的根拠が明示されなければいけない、と思っております。
それでは何が必要なのか。私はこう思います。
あらゆる料理、食材などに対して‘美味しい’‘旨い’という表現を極力さけるべきだということです。生産者や料理人も固有の形容詞をもつべきです。‘美味しい’のは当たり前として、どのような条件のもとで生産・調理されたから他と異なるのか、それを生産者や料理人自身の言葉で語れなくてはなりません。そしてそれらの条件や味覚の表現をどんな人にも共通して認識してもらえるような基準を作るべきです。
その為には明晰な言語と厳格な基準を設けることが必要だと思います。
フランスには、明晰ならざるものはフランス語にあらず、という表現もあります。一方、言葉には言霊が宿る、として、理より情とか和とかを重んじる精神構造をもつ日本人にとっては、こうした作業は大変な苦労を要するかもしれません。しかし、日本語の素晴らしさを残しつつ、一方では怜悧な理性によって冷徹に客観を追及する手段としての言語の役割を確立する必要性があるのではないでしょうか。
とりわけ地域にとって、そうした取り組みが重要になると信じております。
こうした事態は、実は味覚の問題に留まるものではありません。多様な豊かさを持つ日本文化が、その価値を自らアピールするためには、的確にそれを評価し表現する基準と言語を持ち合わせる必要があると思っております。
成本様は頻繁に駅長コラムへご投稿頂いており、その中で地域での懸命なお取り組み姿勢と本質を突いた問題点をご披露くださっています。私が常々感謝と尊敬の念を抱いている方の一人です。
お伺いした際、成本様行きつけのレストラン‘まりーな亭’で食事をご一緒させていただきました。‘まりーな亭’はホームページ上でも紹介してくださっています。
http://www.michi-club.jp/detail/station.php?stationid=000083
この食事会には、田村菓子舗三代目の田村さん、そして‘まりーな亭’の宇都宮オーナーシェフも加わってくださり、さながらタウンミーティングようなの雰囲気の中、延々4時間に亘り色々な話をしました。
話が地域産品や郷土料理に及んだとき、成本様より‘地域では自分達が作った料理、米、野菜、果物は皆この世で一番美味しいと胸を張っているが、果たしてそれだけで良いのか’というご意見が挙がりました。大変興味深いご指摘でした。
この点について成本様と議論を深めることとなりました。その時の話を踏まえ、本日のコラムでは‘美味しさ’について述べたいと思います。
私は全国津々浦々飛び回っております。各地で出会う地域の料理は何れも珍しく、そしてありがたく、そして美味しいと思っています。しかし、一方でその美味しさとは何なのか、実は私はずっと考えてきました。
料理を表現する言葉には、甘い、塩辛い、しょっぱい、苦い、酸っぱいなどがあります。それらの言葉を超えたところに‘美味しい‘という言葉が共通して 君臨してしまうと、全ての料理は「美味しい」か「美味しくない」かに集約されてしまいます。とりわけ我々日本人は基本的には同じような食文化を原点に持っていますのでそれ以外の表現を上手に生み出して来なかったのではないか、と感じてしまうのです。
たとえばアラブ料理です。羊料理には独特の臭みがあり、現地の人たちの味覚はその臭みそのものを愛好するのですが、大抵の日本人にとってはその独特の匂いは親しみのないものです。日本人がアラブの羊料理の美味しさを堪能するためには時間と経験が必要です。
また、かのフランス料理にしても、鳩だとかジビエだとか腎臓とかが出てくるとやはり独特の臭みと苦味があり、これも本当に味わうには経験を要します。
このような異文化の食については、単に‘美味しい’と表現しても、‘でもこれは主観でしょう’と容易に異論が出てくる可能性があります。また一方で、その美味しさを堪能できないことは食文化の違いに過ぎません。従って、食文化の相異を尊重する立場からは、‘美味しい’とは別の表現を使うことが望ましいのです。
しかるに日本料理。日本人であれば殆どの料理が許容範囲内にあります。たとえば「いしり」と呼ばれる能登半島の魚醤などは一見すると強烈な発酵臭を持ってはいますが、地元の料理人の手に掛かれば間違いなく美味しいです。
また、お米はどうでしょうか。色々な地域でその地の地域米を食べる機会があります。どの米も美味しいです。酒にしても地域の人が自信を持って紹介する地酒は外れはありません。果物もしかりです。
しかしそうすると地元の食品や料理は全て美味しいということになってしまい、差別化は難しくなります。
さて、再びフランスの話。フランスと言ったらワイン文化の中心です。生産量であればお隣のイタリアの方が多いですし、歴史でいえば中近東やギリシャの方がよっぽど古いかもしれません。しかし、ワインといったらフランスが一番です。それに異論を呈する人はワインを知らない人だと烙印されてしまうほど、フランスワインは絶対的な力を持っています。
何故か? それは生産量でもなく歴史の古さでもありません。
美味しさというものを学問的に追求しそして評定基準をしっかり作った初めての国がフランスだからです。もっともそれ以前にも、ブルゴーニュのシャンベルタンをナポレオンがこよなく愛し戦場にも必ず持参したとか、駐仏大使だったトーマスジェファーソン第三代米大統領が離任の際にグラーブのオーブリオンを大量に酒樽でアメリカへ持ち帰ったとか、そんな逸話がフランスワインの権威や伝説を生み出した、ということも事実です。
しかし、この世にフランスワインが君臨しているのは、19世紀半ばのパリ万博に備えて、ボルドーにおける格付け作業を地元のワイン取引業者卸組合が行ったからです。彼らはその作業をするに当たり、味、色、香りにおいて厳格な基準を設けました。単なる美味しいという主観的な基準を初めて排除したとも言えます。そうしなければボルドーは、伝統ある産地であるブルゴーニュに勝ち目がなかったからです。
その後は フランス国家を挙げて、全土のワイン及び生産地を対象に、品種、 成分、地質、土壌、 気候、湿度、温度、日照時間、醸造方法等を調査し独自の品質管理制度(AOC)を確立しました。 このような地道な学究と品質維持向上の努力とが相俟って、フランスはワイン王国となることが出来たのです。技術と資本だけでなく言語力、文化力の違いが現在の地位を築いたとも言えます。
ところで、日本ではいまだに‘このワインは美味しい’という表現を平気で使う人がいますが、フランスでは美味しいとは言いません。‘美味しい’に当たる単語である‘Bon’という表現は、テースティングの時にのみ使われ、ソムリエから提案されたボトルをこのまま頂きますよ、という意味合いの言い回しになります。否定形の‘Pas Bon’も味の良し悪しではなく、酸化が進み過ぎているので受け取れない、そんな意味に当たります。
もっともワインの大家なら、保存状態まで分かった上で厳しく‘Non’ということもあるでしょうが。
それでは、日本の料理と素材に話を戻しましょう。地域の人が一生懸命お作りになったものには、基本的に味や品質の面で間違いはありません。しかし、生産や調理の方法において、たとえば、成分、糖度、気候、気温、土壌、農薬散布や施肥の方法、技術、手入れ、伝統、等々、それぞれについて異なるにも関わらず、その帰結とする表現が全て‘美味しい’ということに行き着くのであれば、それはいつになっても本質的な差別化はできないということとなります。
もともと有名な地域は断然有利ですが、そうでない他の地域の場合は、相当な努力をしても‘美味しい’の一言で片付けられてしまい、なかなか浮かばれないということになります。
ここで‘浮かばれる’‘浮かばれない’と言ったのは、マーケットで高く売れるか安値で引き取られるかと言うこととも同義で、地域にとっては死活問題です。それでも現実には、国産米でも品種や産地によって数倍の価格の差がついています。本当にそれほど価値に差があるかどうか、私の舌では判別できません。同じ海域で獲れる魚介類も、水揚げ地が違うだけで異なった価格が付くという話をよく聞きます。
そうした現象を‘ブランド力の違い’と言って納得する人が多いですが、私は常々、本来のブランドとは単なる雰囲気だけでなく、その前提としての科学的根拠が明示されなければいけない、と思っております。
それでは何が必要なのか。私はこう思います。
あらゆる料理、食材などに対して‘美味しい’‘旨い’という表現を極力さけるべきだということです。生産者や料理人も固有の形容詞をもつべきです。‘美味しい’のは当たり前として、どのような条件のもとで生産・調理されたから他と異なるのか、それを生産者や料理人自身の言葉で語れなくてはなりません。そしてそれらの条件や味覚の表現をどんな人にも共通して認識してもらえるような基準を作るべきです。
その為には明晰な言語と厳格な基準を設けることが必要だと思います。
フランスには、明晰ならざるものはフランス語にあらず、という表現もあります。一方、言葉には言霊が宿る、として、理より情とか和とかを重んじる精神構造をもつ日本人にとっては、こうした作業は大変な苦労を要するかもしれません。しかし、日本語の素晴らしさを残しつつ、一方では怜悧な理性によって冷徹に客観を追及する手段としての言語の役割を確立する必要性があるのではないでしょうか。
とりわけ地域にとって、そうした取り組みが重要になると信じております。
こうした事態は、実は味覚の問題に留まるものではありません。多様な豊かさを持つ日本文化が、その価値を自らアピールするためには、的確にそれを評価し表現する基準と言語を持ち合わせる必要があると思っております。
執筆者
未知倶楽部室 室長 賦勺尚樹